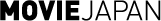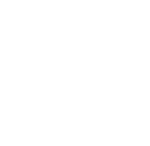- 東京 皇居千鳥ヶ淵 灯ろう流し
- 皇居千鳥ヶ淵 灯ろう流しは、皇居のお濠で毎年夏に開催されます。初めて開催されたのは昭和33年、戦後の人々の心を癒す目的ではじまりました。
2,000個以上もの灯ろうがお濠に浮かんでゆっくりと流れていく幻想的な光景を眺めることができます。
- 北海道 阿寒湖
- 阿寒湖は火山の噴火によって生まれ、周りを雌阿寒岳・雄阿寒岳に囲まれています。また阿寒湖は藻が丸くなるマリモで有名です。真夏も涼しく、冬は一面の氷に覆われ、氷の上にテントを張り穴をあけてワカサギ釣り。春先には砕氷クルーズもあります。
- 北海道 美瑛 白金青い池
- 十勝岳の防災工事でできた池は不思議なほど青く、立ち枯れのカラマツとあいまって幻想的な風景となりました。雪融け水が多く流れ込む春は、少し緑色のブルーに。初夏はライトブルーに。秋は紅葉に彩られ。冬は凍結して一面白い世界に。四季折々のBIEI BLUEが楽しめます。
- 北海道 根室 明治公園
- 1875年、北海道内で2番目となる牧場として設立され、現在は市民公園として利用されています。かわいらしいデザインの3基のサイロはレンガ積みとしては日本国内最大級であり、国の登録有形文化財、近代化産業遺産に認定されています。日本の歴史公園100選にも選ばれています。
- 岩手 厳美渓
- 厳美渓は、栗駒山から流れる磐井川が巨岩を侵食し、生まれました。春は桜と雪解け水、夏は涼しげな渓流のせせらぎ、秋には色づく山々、冬には水墨画のような景色と、四季折々それぞれの風情が楽しむことができます。名物かっこうだんごは、対岸のお店に注文と代金を入れて木槌を鳴らし、ロープで送ると注文しただんごとお茶が降りてきます。
- 山梨 西湖いやしの里根場
- 西湖いやしの里根場は、河口湖近くにある野外博物館です。かつては養蚕が盛んであり、2階部分に窓を設けた約20棟の茅葺民家が並びます。民家ではそれぞれ工芸品の展示や資料館を設けています。茅葺民家のうちの1棟は国の登録有形文化財に登録されています。四季折々の美しい自然の色彩と富士山、のどかな風景が広がります。
- 京都 貴船神社七夕笹飾り
- 貴船神社は、京都の山間部に位置し、京の奥座敷とも呼ばれる場所です。鴨川の源流である貴船川や緑豊かな自然により、夏場でも清涼感に溢れる場所です。貴船神社では毎年7月に夜間特別参拝を実施しています。七夕飾りをライトアップして美しい夏夜を楽しむイベントです。境内を淡く彩る笹と短冊が参拝客を迎えてくれます。
- 岡山 牛窓
- 牛窓は温暖な気候と、牛窓から見える瀬戸内海の海に点在する島の景色の美しさから日本のエーゲ海と言われています。西日本最大級のヨットハーバーや瀬戸内海の多島美を一望出来るオリーブ園でエーゲ海を感じる一方、かつて港町として栄えた頃の風情を残す「しおまち唐琴通り」もあり、多彩な顔を持ちあわせています。
- 鹿児島 種子島 千座の岩屋
- 波に浸食された奇岩の広がる「千座の岩屋」は種子島最大の海蝕洞窟で、千人座れる広さからその名で呼ばれます。洞窟に入れるのは干潮時刻の前後2時間のみ。洞窟内は自然が作り上げた岩の造形美と、反響する波の音により幻想的な雰囲気を漂わせています。枝分かれした洞窟からは、沖合いに散らばる岩礁や美しい海岸を展望できます。
- 鹿児島 種子島 浦田海水浴場
- 種子島の北端にある浦田海水浴場は日本の水浴場88選の一つで、砂丘の白い砂浜と青い空がまぶしいほど美しく、海の透明度も抜群の海水浴場です。緑の山に囲まれた入江の奥に位置するため、静かで穏やかな波音を聞きながら海水浴やシュノーケリングや釣り、キャンプなど様々な楽しみ方が出来ます。
- 鹿児島 種子島 マングローブ原生林
- 南種子町の広大な敷地に生い茂るマングローブは、メヒルギの一種のみ。自生地としては種子島が北限地と言われていて「種子島のマングローブ林」として「日本重要湿地500」にも選ばれています。近年「マングローブパーク」として整備され、敷地内のボードウォークでマングローブの中を散策したりシーカヤック体験も楽しめます。
- 福岡 博多祇園山笠
- 博多祇園山笠は、ユネスコ無形文化遺産に登録されている700年以上の伝統ある祭りです。祭りの最終日に行われる「追い山」では重さ1トンにも及ぶ舁き山笠が夜明けの博多の町を疾走します。舁き手たちの「オイサ!」の掛け声を聞きつけ、沿道では勢水が打ちまかれます。びしょ濡れになりながら駆け抜ける山笠の姿は圧巻です。