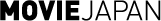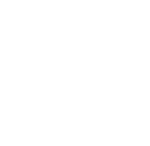- 大阪 天神祭
- 天神祭は1000年以上続く日本の三大祭りのひとつです。学問の神様である菅原道真の命日付近に行われるもので、道真公にちなんだ梅鉢形に開く花火などが打ち上げられます。奉納花火の打ち上げ数は約5000発。天神祭では3000人もの行列によってなる陸渡御と、100隻もの船が水上を渡る船渡御が行われ、祭りの見所となっています。
- 宮城 塩竈みなと祭
- 塩竈みなと祭は、「管絃祭」「貴船まつり」と合わせて、日本三大船祭りとされているものです。毎年、海の日に開催され、神輿が市内を練り歩いた後、塩竈港から御座船に乗り入れて海上を回ります。海上では100隻を超える漁船が大漁旗をあげて追随し、太鼓や笛で盛り上げます。パレードや花火などもあり、見所満載の祭りです。
- 愛媛 うわじま牛鬼まつり
- うわじま牛鬼まつりは、毎年7月にガイヤカーニバルを皮切りに行われる夏祭りです。四国有数の夏祭りとされていて、祭りが開催される3日間は何体もの牛鬼が市内を練り歩きます。また、伝統の宇和島おどりや宇和海を彩る花火なども見物です。最終日には三体の御輿が登場し、松明の火を灯しながら荘厳な走り込みが行われます。
- 富山 立山の夏
- 立山は標高3003mを誇る日本三霊山のひとつです。また、日本百名山にも指定されており、大パノラマを楽しめる世界的な山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」もあります。トロリーバスやケーブルカーで気楽に登山を楽しむことが可能です。また、夏のみくりが池は雪解け水を湛えて、美しい立山の姿を水面に映し出します。
- 岩手 三陸 北限の海女
- 北限の海女は、小袖海岸で活躍する海女のことを指す言葉です。距離180㎞にも及ぶ陸中海岸は世界三大漁場のひとつとして数えられていて、海女たちは豊かな海で育ったウニやアワビなどを巧みな技術で採り入れます。三陸の海は冷たく、素早い潜水技術が必要です。ベテランの海女はひとかきで2mあまりも進むと言われています。
- 若狭 蘇洞門
- 蘇洞門は若狭湾国定公園に含まれる海岸景勝地で、全長約6㎞に及び「若狭蘇洞門」の名で国の名勝に指定されています。蘇洞門は、花崗岩が波に浸食されて柱状に形成されたもので、海蝕洞である大門、小門、夫婦亀岩、獅子岩、唐船島などと呼ばれる自然岩の見所が多くあります。遊覧船で奇岩を間近に観賞することも可能です。
- 北海道 富良野 日の出ラベンダー園
- 上富良野町の日の出公園は、恋人の聖地と呼ばれています。また、富良野で最初にラベンダーの栽培をはじめた地でもあり、園内には記念碑も残されています。展望台からはラベンダー畑と共に十勝岳連邦を間近に眺めることができます。展望台にある真っ白なアーチ型のモニュメント「愛の鐘」では結婚式が行われる日もあります。
- 北海道 美瑛 四季彩の丘
- 展望花畑「四季彩の丘」は美瑛にある観光名所です。東京ドーム3個分もの広さを有し、年間約30種類の植物が美しく咲き誇ります。色ごとに栽培されているので、花びらの色による壮大な虹のようなストライプ模様の絶景を楽しめます。花の見ごろは夏ですが、冬には雪化粧をした山々と花のコントラストを楽しむこともできます。
- 和歌山 那智の火祭
- 那智の火祭りは正式名称「扇祭」と呼ばれ、無形民俗文化財に指定されています。水を生命の源、火を万物の活力と見立て、五穀豊穣を祈念する祭りです。白装束を着た男性が重さ50㎏にも及ぶ燃え盛る大松明を担ぎ、那智の滝に続く石段をハリヤーの掛け声と共に練り歩きます。12体の扇神輿には熊野の神々が宿るとされています。
- 大阪 箕面大滝
- 箕面の滝は、大阪北部に位置する明治の森箕面国定公園内にあります。日本の滝百選のひとつで、天下の名瀑とも呼ばれています。滝の落差は33mもあり、元々は修験道の道場でもありました。箕面の名前は、木々の間から落ちる水の姿が「蓑」に似ていることからつけられたと言われています。秋の紅葉が美しいことでも有名です。
- 静岡 法多山尊永寺 万灯祭
- 法多山尊永寺は高野山真言宗の別格本山です。法多山では7月10日が1年で最もご利益のある日とされています。また、この日に本尊厄除観世音に灯りを献することでご利益は倍増するとも言われています。万灯祭は本堂前に何千基もの灯籠が奉納される夏の風物詩です。境内に灯る幻想的な灯籠の他にも、寄席などの催しで賑わいます。
- 奈良 清納の滝
- 清納の滝は豊富な水量と広い滝壺を持ち、別名「瀬野の滝」「マイナスイオンの滝」と呼ばれています。落差は15mほどですが、水量が多いため水しぶきが広く霧状に降り注ぎます。関西屈指の避暑地で、青く澄んだ滝の近くには「大野出合のヴィーナス」と呼ばれる女性のように見える岩もあり、見ると幸運になるとされています。