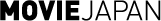雪景色
- 岐阜 雪の白川郷
- 世界遺産 白川郷の冬は、合掌造りの屋根に白い雪が降り積もり、まるで絵本のような風景が広がります。
合掌とは、掌を合わせたように三角形に組む丸太組みを「合掌」と呼ぶことから来たと推測されています。
夜はライトアップされ、まさにファンタジーの世界になります。
- 山形 月山志津温泉 雪旅籠の灯り
- 月山志津地区は四百年以上前から出羽三山で修行する三山行者の宿場町でした。志津の冬は有数の豪雪地帯であり、その雪を使って当時の町並みを再現したのが雪旅籠の灯りです。雪は宝であり大切な資源であることを伝えながら、少しでも雪を好きになってほしいという思いで、毎年2月に催されます。
- 東京 皇居 千鳥ヶ淵の雪桜
- 何年かに一度、東京では桜が咲いた後に雪が降ることがあります。2020年にも満開の桜に雪が積もりました。皇居のお濠の深い緑と、桜のピンク、白い雪が幻想的な風景を創り出します。古くから、桜の時期に雪が降ることを「桜隠し」といい、春の季語でもあります。
- 北海道 冬の函館港
- 函館はその文化の多くが箱館港開港の歴史に集約されます。坂道で有名な函館ですが、中でも八幡坂は、見下ろす函館港、元町の教会群、背後に見上げる函館山と、函館を代表するビュースポットです。国の重要文化財聖ハリストス教会など歴史的な建造物も数多く残り、赤レンガが特徴的な「金森倉庫群」は地元の人たちの憩いの場所でもあります。
- 山形 まんだらの里 雪の芸術祭
- 「まんだらの里」は、東村山郡山辺町の山道を抜けた先にあります。雪の芸術祭では、ライトアップされた雪のオブジェや、花火の打ち上げ、ステージでの様々なイベントなどが楽しめます。そして、お祭のハイライトは、夜空を彩るスカイランタンの打ち上げ。冬の夜空に舞うランタンの幻想的な風景に、ただただ魅了されてしまいます。
- 福島 会津 雪の鶴ヶ城
- 鶴ヶ城の赤瓦と白雪のコントラストは冬ならではの表情です。城の周辺、本丸の松に施された「枝つり」も、冬の風物詩として知られています。
- 北海道 さっぽろ雪まつり
- 毎年2月の寒いさっぽろの街に、大きな雪像が約195基並びます。雪の量にして5tトラック6000台分。開催も70回を超え、年々その規模は大きくなっています。そんな雪まつりも最初は地元の中・高校生が6つの石像を大通り公園に設置したことが始まりでした。現在では世界的なイベントとなり、来場者数は250万人。さて何から見ましょうか。
- 北海道 さっぽろ羊ヶ丘展望台
- 一面銀世界のさっぽろ羊ヶ丘展望台。このパノラマビューの丘で「青年よ大志を抱け」と右手をあげているのは北海道開拓の父と呼ばれる、かのクラーク博士。札幌農学校(現北海道大学)の初代教頭として招かれた彼は、教え子との別れの時、この言葉を馬の上から叫んだと言われています。
ちなみに右手の指は一本で指していないので、記念撮影の際は気を付けてくださいね。
- 長野 志賀高原 地獄谷温泉の猿 スノーモンキー
- 地獄谷温泉では、凍える猿が、まるで人間のように温泉でゆったりくつろぐ姿を見ることができます。
雪をかぶりながら温泉に浸かる猿は「スノーモンキー」と呼ばれて親しまれています。
- 福島 会津 絵ろうそくまつり
- 500年の歴史を持つ会津の伝統的工芸品「会津絵ろうそく」。
鶴ヶ城の敷地に約10000本の絵ろうそくが幻想的に灯る「絵ろうそくまつり」は会津の冬の風物詩です。
- 福島 冬の奥会津
- 奥会津は深い山あいを只見川が縫うように流れる秘境。
日本でも有数の豪雪地帯で、特に冬は雪化粧した木々が広がり、穏やかな水面は鏡のように美しく風景を映し出します。
まるで水墨画を見ているような神秘的な絶景です。
- 金沢 雪の兼六園と金沢城
- 冬を迎える前に行われる「雪吊り」。
枝に縄を施し、北陸地方特有の湿度のある雪から守ります。
ライトアップされると、またいつもとは違った冬ならではの風景を楽しむことができます。