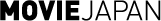たべもの
- 高知 土佐のおきゃく
- おきゃくとは土佐弁で宴会のことをいい、土佐のおきゃくは高知の街を会場にした、年に一度のお祭りです。商店街や公園などに畳が敷かれ、座敷やこたつが置かれるなど、至るところで酒を酌み交わし酒文化に浸ります。土佐の酒の神様「べろべろの神様」に見守られ、趣向を凝らした数々のイベントも訪れた人を楽しませます。
- 高知 ひろめ市場
- ひろめ市場は高知城から徒歩2分に位置しています。日曜市にも隣接した観光施設で、郷土料理をはじめとする和洋中様々な飲食店や、物販店が軒を連ねます。
市場内で購入した飲食物は広場・通り・横丁で自由に食事ができ、地元民と観光客が酒を酌み交わすにぎやかな雰囲気で、週末には巨大宴会場と化します。
- 沖縄 那覇 公設市場
- 2023年春にリニューアル予定の公設市場は、沖縄の台所と呼ばれ、多くの観光客も訪れます。「持ち上げ」は1階で購入した肉や鮮魚を2階の飲食店に持ち込んでその場で調理してもらって食べることができるシステム。そして公設市場の魅力は、人情。買い物客がシーブン(おまけ)交渉したり売り手が感謝の気持ちでシーブンしたりと会話を楽しみながら気さくに買い物ができます。
- 埼玉 浦和の鰻
- 土用の丑の日に食べられる鰻は日本を代表する食文化です。武士の文化の関東では腹から捌くことはせず背中から捌きます。また料理法も関東は蒸し、関西は蒸さずに焼き上げます。全国に鰻の名所はたくさんありますが、浦和もそのひとつ。古くは中山道を行きかう人たちがわざわざ寄った200年の歴史をもつ鰻です。
- 和菓子づくり
- 和菓子はおいしいだけではなく、季節を見た目も美しく表現する日本らしい食文化です。京都では多くのところで和菓子作りが体験できます。映像は氷餅を使った和菓子。氷餅は割ると粉々になり、小さなカケラが雪の結晶のようにキラキラ輝きます。
- 秋の絶景いばらき旅
- 茨城県立歴史館、はぎビレッジ、こやま湖 ボートクルーズ、うのしまヴィラ、さくら宇宙公園、日立駅、袋田の滝、竜神大吊橋、酒列磯前神社、ほしいも神社
- 高知 皿鉢料理
- 有名な鰹のたたきをはじめとした郷土料理が大皿を埋め尽くす皿鉢料理は料理の名前でなく、その大きなお皿に盛り付けられる様式のことを指します。起源は武家の時代に遡り、当時は土佐だけのものではなく、全国でお祝いの日に出される料理でした。その後土佐に定着。その家の裕福さを表すものでもあり伊万里焼や有田焼で客をもてなしたと言います。
- 愛知 菜飯田楽
- 菜飯田楽とは、乾燥させた大根葉をご飯と一緒に炊き込んだものと、味噌田楽を組み合わせた料理のことを指します。東三河地方が発祥の地とされ、古くよりこの地で愛されてきました。少し塩気のある菜飯と、こっくりとした甘い八丁味噌が塗られた田楽は、最高の組み合わせです。
- 山梨 甘草屋敷の吊るし柿
- 山梨県甲州市の旧高野家住宅甘草屋敷は茅葺屋根の歴史的建造物で、秋になると名物ころ柿が軒先を埋めるように吊るされます。ころ柿の言われは、風に吹かれてころころ回る姿や、この後成型のためにころころ転がすから、など諸説あります。大きな百目柿で甘くて美味しいのが特徴です。
- 北海道 函館朝市
- 北海道、港町、当然海鮮が有名な函館朝市ですが、そのルーツは戦後、農家の人々が集まり野菜の販売を始めたことにあります。今でも海鮮に限らず青果品や加工品も多く扱われるのはそのためです。時代と共に「市民の台所」として親しまれるようになり、今では国内外から年間約200万人がこの市場を訪れます。
- 青森 せんべい汁
- せんべい汁は青森県八戸市周辺で江戸時代後期に生まれた、伝統的な郷土料理で、専用のかやき煎餅を用いて醤油味で煮立てた汁です。鶏や豚の出汁でごぼう、きのこ、ネギの具材と共に煮立てます。汁を吸ったせんべいはすいとんより歯ごたえがでます。