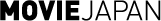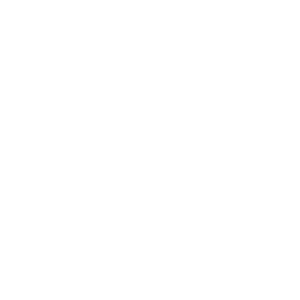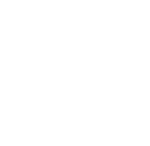- 静岡 法多山尊永寺 万灯祭
- 法多山尊永寺は高野山真言宗の別格本山です。法多山では7月10日が1年で最もご利益のある日とされています。また、この日に本尊厄除観世音に灯りを献することでご利益は倍増するとも言われています。万灯祭は本堂前に何千基もの灯籠が奉納される夏の風物詩です。境内に灯る幻想的な灯籠の他にも、寄席などの催しで賑わいます。
- 東京 上野 入谷朝顔まつり
- 入谷朝顔まつりは、七夕の季節に東京台東区の入谷鬼子母神周辺で行われる祭事です。早朝5時から23時までと、一日中楽しめるこの祭りは、江戸時代後期からはじまりました。道々に並べられる色鮮やかな朝顔の数は12万鉢にも及び、屋台や露店も朝顔に負けじと賑やかに祭りを盛り上げます。夏の風物詩を味わう伝統の祭りです。
- 奈良 ならまち 身代わり申
- 江戸時代の町並が残る奈良町では、軒先に赤いぬいぐるみが吊るされています。これは庚申さんの使いである猿を模った魔除けです。家中に災いが入らないように吊るすことから「身代り申」と呼ばれています。身につけることで災難を除けられたり、背中側に願い事を書くことで願いが叶ったりするという言い伝えも残っています。
- 東京 浅草寺ほおずき市
- 浅草寺のほおずき市は、1日で46000日分の功徳を得られるとされる縁日に合わせて行われるものです。46000日というのは、126年、つまり人間の一生分以上の功徳が得られる日であると言えます。ほおずきは健康祈願や、盆の棚飾りに用いられます。境内には朝から晩まで、ほおずき売りたちの賑やかな声が響き渡ります。
- 千葉 南房総白浜海女祭り
- 南房総白浜海女まつりは、50年以上続く海の安全と豊漁祈願をする祭典です。白装束を身に纏った約100名の海女さんが松明を持って夜の海を泳ぐ大夜泳は厳かな雰囲気が漂います。また、郷土民謡白浜音頭総踊りや、龍神の舞など、地元に根ざした伝統の催しも多く開かれ、フィナーレには打ち上げ花火が夜の海に美しく華開きます。
- 東京大神宮 七夕飾り
- 東京大神宮では、毎年7月に七夕祈願祭を行います。これは心願成就と除災招福を願う祭りです。織姫星と彦星が年に一度7月7日の夜に再会するという伝説になぞらえて、短冊に願い事を書き、笹竹に結び付けます。沢山の願いが吊るされた笹竹は東京大神宮の拝殿前に飾られ、夜には幻想的な雰囲気を纏ってライトアップされます。
- 東京 浅草 三社祭
- 三社祭は浅草神社で毎年5月に3日間を通して行われる勇壮な祭り行事です。東京の初夏を代表する風物詩のひとつとして広く知られています。
囃子屋台をはじめ、華やかな舞いを踊る大行列が浅草の町を練り歩きます。また、伝統的な式典が行われたり、戦前に徳川家光公より寄進された歴史ある神輿の担ぎ出しがされたりします。
- 新潟 佐渡 たらい舟
- たらい船とは、洗濯桶の「たらい」を船代わりにしたものです。岩礁の多い入り江で漁をするため、小回りと安定性を考えて造られました。
伝統衣装を身に纏った女船頭さんの漕ぐ船は500㎏まで耐えられます。実際にたらい船漕ぎ体験をすることも可能で、うまく前に進んだらその場でたらい船の操縦士免許を貰うことができます。
- 神奈川 箱根神社節分祭
- 箱根神社では、2月の節分の日に鬼退治の節分祭を執り行います。これはその昔、宮中で行われていた追儺式、金太郎伝説の鬼やらいという儀式に由来している行事です。まだ雪の残る凛とした空気の中、伝統的な儀式はもちろん、水上スキーを使った鬼退治の豆まきも行われています。
- 宮城 東北輓馬競技大会
- 毎年、桜まつりのメインイベントとして開催される、自馬の力を競う輓馬競技大会。馬たちは、最大で975kgにもなる重量をのせたソリを引き、全長120mのコースでタイムを競います。騎手と馬、まさに人馬一体となったその姿に、観衆からは大きな声援と歓声が巻き起こります。
- 徳島 わんわん凧
- 江戸時代、阿波名物鳴門大凧には地域ごとにたくさんの種類があり、その中で撫養町のわんわん凧は横綱と言われました。かわいらしい名前は、蓮花寺本堂再建のお祝いに、棟梁の又右衛門は大凧をあげ、丹塗りの椀(わん)に鏡餅を盛って人々に振る舞ったことが由来と言われています。今では元旦を祝う行事として親しまれています。
- 徳島 門松作り
- 門松はお正月に年神様を迎える目印であり、またその依り代として家の前に置かれます。平安時代頃よりあったとされ、初めは松のみを飾るものでした。松は葉が落ちないので縁起が良く、神の宿る木と言われます。また繁栄を意味する竹を斜めに切ったのは徳川家康と言われ、負けた戦の悔しさを忘れないためでした。