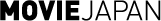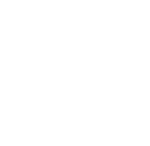- 東京 目黒川の夜桜
- 池尻大橋から中目黒にかけての目黒川の桜並木は、夜になるとライトアップされ、たくさんの飲食店も立ち並び、多くの人で賑わいます。川面に映るぼんぼりの灯りと桜が、とても美しく映えます。
- 高知 土佐のおきゃく
- おきゃくとは土佐弁で宴会のことをいい、土佐のおきゃくは高知の街を会場にした、年に一度のお祭りです。商店街や公園などに畳が敷かれ、座敷やこたつが置かれるなど、至るところで酒を酌み交わし酒文化に浸ります。土佐の酒の神様「べろべろの神様」に見守られ、趣向を凝らした数々のイベントも訪れた人を楽しませます。
- 千葉 房総 小湊鉄道飯給駅
- 小湊鉄道にある飯給(いたぶ)駅は、普段は1日の降りる方が5人程度の小さな無人駅ですが、地元のボランティアの方たちの見事な手入れで、明るくかわいい駅になっています。桜の時期には、駅前の田んぼに桜と列車が映り込み、のどかで美しい風景が見られます。世界一広いトイレ(女性用)もあります。
- 千葉 房総 小湊鉄道飯給駅 桜ライトアップ
- 小湊鉄道飯給(いたぶ)駅の桜のライトアップは、駅前の田んぼに列車と桜が映り込み、日が沈むとまるで物語の中に迷い込んだような風景になります。ゆっくりとホームに滑り込んでくる列車は、走り出して、そのまま星空に上っていきそうな、とても幻想的な情景です。
- 東京 上野恩賜公園の桜
- 上野の山は、江戸時代から桜の名所として知られていました。天海僧正が吉野山から移植させたといわれ、約800本の桜が園内を彩ります。ソメイヨシノだけでなく40種以上の桜が楽しめます。公園中央の桜通りが有名ですが、不忍池、国立博物館もとてもきれいです。
- 東京 隅田公園 東京スカイツリーと桜
- 隅田公園は隅田川沿い、浅草側と左岸の向島にあります。夏の隅田川花火大会が有名ですが、春は東京スカイツリーと桜のコラボレーションのベストスポットでもあります。公園内の庭園は水戸徳川邸内の池などを利用して造られています。関東大震災後で屋敷が全壊するまで代々ここに住んでいたと伝えられています。
- 東京 日本橋江戸桜通りの夜桜
- お江戸日本橋、西は常盤橋から東の昭和通りまで、大通りと老舗の路地を桜並木が続きます。江戸時代の市川團十郎のお家芸、助六由縁江戸桜にちなんで名づけられたといいます。特に中央通り西の日本橋三越本店本館、三井本館など石造りの歴史的建造物が建ち並ぶ道はライトアップされてとても美しくなります。
- 東京 皇居 千鳥ヶ淵の雪桜
- 何年かに一度、東京では桜が咲いた後に雪が降ることがあります。2020年にも満開の桜に雪が積もりました。皇居のお濠の深い緑と、桜のピンク、白い雪が幻想的な風景を創り出します。古くから、桜の時期に雪が降ることを「桜隠し」といい、春の季語でもあります。
- 京都 市比賣神社 ひいなまつり
- あかりをつけましょ、ぼんぼりに。祀られる五祭神全てが女神であることから、女人厄除けの神社とされる市比賣(いちひめ)神社で行われるひいなまつりでは、雛に扮した人に着付けがされ、五人囃子の笛太鼓に三人官女が舞います。ひな壇に人々が揃い天皇皇后の結婚の儀であったとされる「今日は私のはれ姿」が艶やかに目の前に再現されるのです。
- 東京 目黒川の桜
- 春になると一本の川を覆い尽くすかのように桜が咲き誇ります。目黒川周辺は東京らしいお店やビルが立ち並ぶ場所ですが、一本道が変わると景色が一変するのです。大橋から下目黒までのおよそ4kmを彩るのは800本のソメイヨシノ。夜にはライトアップがされ昼間とはまた違う幻想的な光景を楽しむことができます。
- 神奈川 鎌倉大仏と桜
- 1252年に建立されたといわれる「鎌倉の大仏」は、国宝銅造阿弥陀如来坐像を本尊に持つ高徳院にあります。当初は大仏殿の中にありましたが、台風や津波で倒壊し、露坐の大仏となりました。その高さは13mあり、境内約60本のソメイヨシノやしだれ桜が見頃を迎えると、大仏様と桜と青空の美しいコントラストを楽しめます。