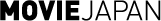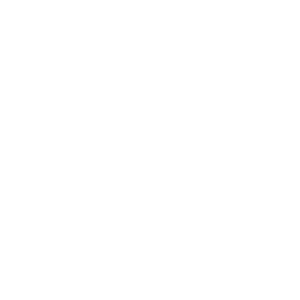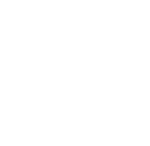- 七五三
- 七五三は古くより行われていた数え年3歳で行われた髪置(かみおき)、5歳の袴着(はかまぎ)、7歳の帯解き(おびとき)の子どもの成長を祝う儀式に由来します。
現在では男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳の時に羽織袴や着物を着て、子どもの成長を願って神社にお詣りするなど、家族でお祝いする風習が受け継がれています。
- 福島 相馬野馬追
- 相馬野馬追は、1000年以上の歴史ある祭礼で、相馬中村神社、相馬太田神社、相馬小高神社の三社が軍を編成し行います。初日の出陣式にはじまり、野馬懸や甲冑競馬、神旗争奪戦が行われ、迫力満点の馬術を見ることができます。街中を騎馬武者が行進するお行列などの神事も行われ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。
- 戸隠 忍者の里 チビッ子忍者村
- 戸隠流の忍術は、平安時代末期、戸隠大助によって作られたと言われています。いつの時代も、海外でも人気の忍者は子供たちの憧れ。からくり屋敷に、手裏剣体験、修行の森アスレチックなど、忍者体験ができるテーマパークです。
- 新潟 松之山 むこ投げすみ塗り
- 十日町市松之山温泉では、胴上げされた婿を雪の中へと放り投げる奇習があります。一説には略奪婚の名残であり、村娘を他の村のものに取られた腹いせから始まったと言います。また、その後には薬師堂で塞の神を燃やした灰を、おめでとう、と言いながら皆でお互いの顔へ塗り無病息災を祈る、すみ塗りを行います。黒くなった顔を見つめ合い笑顔が広がります。
- 中秋の名月
- 十五夜(中秋の名月)は四季の中でも特に月がきれいに見える日。日本では古くから月を愛でる風習がありました。お供えのススキは稲穂に似ているから収穫を祈るものとして。また魔除けとして。丸い月見団子は十五夜にちなんで十五個山のように積みます。
- 京都 貴船神社七夕笹飾り
- 貴船神社は、京都の山間部に位置し、京の奥座敷とも呼ばれる場所です。鴨川の源流である貴船川や緑豊かな自然により、夏場でも清涼感に溢れる場所です。貴船神社では毎年7月に夜間特別参拝を実施しています。七夕飾りをライトアップして美しい夏夜を楽しむイベントです。境内を淡く彩る笹と短冊が参拝客を迎えてくれます。
- 京都 市比賣神社 ひいなまつり
- あかりをつけましょ、ぼんぼりに。祀られる五祭神全てが女神であることから、女人厄除けの神社とされる市比賣(いちひめ)神社で行われるひいなまつりでは、雛に扮した人に着付けがされ、五人囃子の笛太鼓に三人官女が舞います。ひな壇に人々が揃い天皇皇后の結婚の儀であったとされる「今日は私のはれ姿」が艶やかに目の前に再現されるのです。
- 東京 神田祭
- 神田祭は京都の祇園祭、大阪の天神祭と並ぶ日本三大祭りのひとつです。天下祭とも呼ばれ、その名称からは江戸幕府の栄華が窺い知れます。平安時代の衣装を身に纏った人々の大行列「神幸祭」は、平安時代の風情が蘇る印象的な光景。神幸祭の翌日には周辺の町からおよそ100基の神輿が担ぎ出され、神田明神へと向かいます。
- 東京 浅草 酉の市
- 威勢の良い掛け声と手拍子が鳴り響く酉の市は各地の鷲神社や大鳥神社で江戸時代から続く行事です。鎌倉時代、日蓮大聖人が国家の平穏無事を祈ったところ、11月の酉の日に鷲妙見大菩薩が現れたことに由来します。神社に並ぶ縁起熊手は運をかっ込む、福をはき込むと言う洒落で開運招福、商売繁盛を祈った、江戸っ子らしい縁起物です。
- 茨城 潮来 嫁入り舟
- 潮来の嫁入り舟は、昭和30年代に水路を利用した嫁入りを行っていた風習を現代に残したものです。「水郷潮来あやめまつり」では、100万株の花菖蒲に囲まれて、白無垢の花嫁が水路を渡ります。道行く人々からの祝福を受け、手漕ぎのサッパ舟で花婿の元へ。バージンロードではなく水路を渡るのは、水郷潮来ならではの光景です。
- 岐阜 高山祭
- 高山祭は、岐阜県で毎年4月に開催される「春の山王祭」と10月開催の「秋の八幡祭」の総称で、日本三大曳山祭、日本三大美祭のひとつとされています。見所は動く陽明門とも呼ばれる祭屋台で、春には12台、秋には11台が絢爛豪華な姿を見せます。夜になると屋台には提灯が灯り、伝統装束を纏った行列は総勢数百名にもなります。