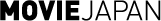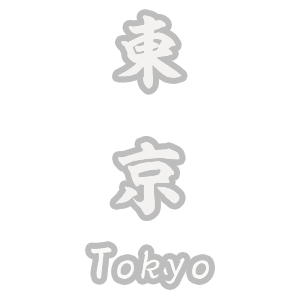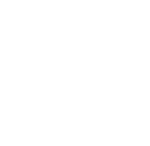- 東京 目黒川の夜桜
- 池尻大橋から中目黒にかけての目黒川の桜並木は、夜になるとライトアップされ、たくさんの飲食店も立ち並び、多くの人で賑わいます。川面に映るぼんぼりの灯りと桜が、とても美しく映えます。
- 東京 神代植物公園バラ園
- 武蔵野の面影が残る深大寺に、広さ48万平方メートル余りの神代植物公園はあります。中でもバラ園は、シンメトリックに設計された沈床式庭園の「本園」、オールドローズ中心の「野生種・オールドローズ園」、国際ばら新品種コンクールのための「国際ばらコンクール花壇」の3つのエリアで構成され、春、秋と楽しむことができる名所です。
- 東京 皇居千鳥ヶ淵 灯ろう流し
- 皇居千鳥ヶ淵 灯ろう流しは、皇居のお濠で毎年夏に開催されます。初めて開催されたのは昭和33年、戦後の人々の心を癒す目的ではじまりました。
2,000個以上もの灯ろうがお濠に浮かんでゆっくりと流れていく幻想的な光景を眺めることができます。
- 東京 深大寺
- 深大寺は、東京都内で二番目に歴史の深い寺で、奈良時代733年に満功上人により天台宗寺院として創建されました。
厄除けとして由緒ある寺であり、毎年3月にある深大寺だるま市も、日本三大だるま市の一つとして有名です。豊富な湧水をつかったお蕎麦屋さんが門前に軒を並べます。
- 東京 上野恩賜公園の桜
- 上野の山は、江戸時代から桜の名所として知られていました。天海僧正が吉野山から移植させたといわれ、約800本の桜が園内を彩ります。ソメイヨシノだけでなく40種以上の桜が楽しめます。公園中央の桜通りが有名ですが、不忍池、国立博物館もとてもきれいです。
- 東京 隅田公園 東京スカイツリーと桜
- 隅田公園は隅田川沿い、浅草側と左岸の向島にあります。夏の隅田川花火大会が有名ですが、春は東京スカイツリーと桜のコラボレーションのベストスポットでもあります。公園内の庭園は水戸徳川邸内の池などを利用して造られています。関東大震災後で屋敷が全壊するまで代々ここに住んでいたと伝えられています。
- 東京 日本橋江戸桜通りの夜桜
- お江戸日本橋、西は常盤橋から東の昭和通りまで、大通りと老舗の路地を桜並木が続きます。江戸時代の市川團十郎のお家芸、助六由縁江戸桜にちなんで名づけられたといいます。特に中央通り西の日本橋三越本店本館、三井本館など石造りの歴史的建造物が建ち並ぶ道はライトアップされてとても美しくなります。
- 東京 皇居 千鳥ヶ淵の雪桜
- 何年かに一度、東京では桜が咲いた後に雪が降ることがあります。2020年にも満開の桜に雪が積もりました。皇居のお濠の深い緑と、桜のピンク、白い雪が幻想的な風景を創り出します。古くから、桜の時期に雪が降ることを「桜隠し」といい、春の季語でもあります。
- 中秋の名月
- 十五夜(中秋の名月)は四季の中でも特に月がきれいに見える日。日本では古くから月を愛でる風習がありました。お供えのススキは稲穂に似ているから収穫を祈るものとして。また魔除けとして。丸い月見団子は十五夜にちなんで十五個山のように積みます。
- 東京 小田急夕日
- 東京からは富士山の良く見える場所がいくつかあります。小田急線世田谷代田駅前もそうです。
家路につく人たちを乗せ、富士山に向かって進む小田急線と、富士山の方向に沈む夕日。年に2回ダイヤモンド富士も見ることができます。ビルが建ち並ぶ前は東京の至る所から富士山が見えていたのでしょう。
- 東京 等々力渓谷
- 田園調布や自由が丘のすぐ近くに、ここは東京か? と思わずにはいられない場所があります。等々力渓谷はたくさんの車が走る環八通りの下を流れます。清流と併せて、春の桜、夏の新緑、秋の紅葉と四季折々の自然を感じることができます。古墳時代の横穴式のお墓も発見されています。
- 東京 多摩川台公園の紫陽花
- 多摩川沿いの大田区多摩川台公園には、7種3000株の紫陽花が咲き誇ります。額あじさいは日本原産の花。花序の周辺部を縁取るように並び、園芸では、額咲きと呼ばれます。花序が球形ですべて装飾花となったおなじみのアジサイは、手まり咲きと呼ばれます。