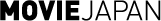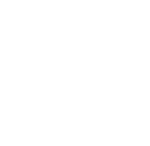- 東京 神代植物公園バラ園
- 武蔵野の面影が残る深大寺に、広さ48万平方メートル余りの神代植物公園はあります。中でもバラ園は、シンメトリックに設計された沈床式庭園の「本園」、オールドローズ中心の「野生種・オールドローズ園」、国際ばら新品種コンクールのための「国際ばらコンクール花壇」の3つのエリアで構成され、春、秋と楽しむことができる名所です。
- 埼玉 秩父 天空のポピー
- 秩父高原牧場(彩の国ふれあい牧場)の標高500mの広大な斜面に、5月から6月にかけて、約1,200万本のポピーが咲き誇ります。
一面に広がるポピーの赤と、澄み渡る青空とのコントラストは、まさに「天空の」という言葉がふさわしい絶景です。
- 福島 相馬野馬追
- 相馬野馬追は、1000年以上の歴史ある祭礼で、相馬中村神社、相馬太田神社、相馬小高神社の三社が軍を編成し行います。初日の出陣式にはじまり、野馬懸や甲冑競馬、神旗争奪戦が行われ、迫力満点の馬術を見ることができます。街中を騎馬武者が行進するお行列などの神事も行われ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。
- 山口 秋吉台
- 秋吉台は500~600m級の山脈に囲まれて盆地状の日本最大のカルスト台地で、主として古生代の石灰岩からなり、台地の地下には雨水によって侵食された鍾乳洞が多数散在しています。
- 東京 等々力渓谷
- 田園調布や自由が丘のすぐ近くに、ここは東京か? と思わずにはいられない場所があります。等々力渓谷はたくさんの車が走る環八通りの下を流れます。清流と併せて、春の桜、夏の新緑、秋の紅葉と四季折々の自然を感じることができます。古墳時代の横穴式のお墓も発見されています。
- 東京 神田祭
- 神田祭は京都の祇園祭、大阪の天神祭と並ぶ日本三大祭りのひとつです。天下祭とも呼ばれ、その名称からは江戸幕府の栄華が窺い知れます。平安時代の衣装を身に纏った人々の大行列「神幸祭」は、平安時代の風情が蘇る印象的な光景。神幸祭の翌日には周辺の町からおよそ100基の神輿が担ぎ出され、神田明神へと向かいます。
- 茨城 潮来 嫁入り舟
- 潮来の嫁入り舟は、昭和30年代に水路を利用した嫁入りを行っていた風習を現代に残したものです。「水郷潮来あやめまつり」では、100万株の花菖蒲に囲まれて、白無垢の花嫁が水路を渡ります。道行く人々からの祝福を受け、手漕ぎのサッパ舟で花婿の元へ。バージンロードではなく水路を渡るのは、水郷潮来ならではの光景です。
- 岐阜 モネの池
- モネの池は、岐阜県の根道神社参道脇にある貯水池です。モネの池というのは通称で、この池に正式な名称はありません。透明度の高い水を湛え、スイレンなどの水生植物が咲き、優雅に鯉が泳ぐ池は、まるでクロード・モネの作品「睡蓮」のモデルとなった池のようだとして、いつしか人々からモネの池と呼ばれるようになりました。
- 徳島 船窪つつじ公園
- 標高1060mに位置する船底形の窪地に、まるで植栽されたかのように群生している約1200株のオンツツジは、国の天然記念物にも指定されています。樹齢400年を超えるものや、一株から20数本の主幹をもつ巨大なオンツツジも多く、これに匹敵する群落は類をみません。5月中旬から見頃を迎え、山肌一面が燃えるような朱色に染まります。
- 群馬 嬬恋村 愛妻の丘
- 嬬恋村はその名から愛妻家の聖地として観光PRを行っています。中でも愛妻の丘は、観る観光スポットではなく、叫ぶ観光スポット。日頃の感謝の思いを広大なキャベツ畑に向かって叫びます。目前には田代湖と見渡す限りのキャベツ畑の絶景が広がります。
- 群馬 嬬恋村 キャベツ畑
- 嬬恋村のキャベツは日本の総出荷量の約半分、首都圏ではなんと80%を占めます。浅間山と青い空を背景に、どこまでも続くなだらかなキャベツ畑はまるで北海道にいるような気分になります。嬬恋のキャベツは甘く柔らかく、地元では「玉菜」とも呼ばれています。
- 群馬 嬬恋村 湯ノ丸高原のレンゲつつじ
- 浅間連峰の西側に位置する湯の丸高原は、爽やかな亜高山帯気候で「花高原」として親しまれています。6月には天然記念物に指定された60万株のレンゲつつじが赤い花を咲かせ全土を紅く染めます。この高原には季節を通じて1000種類以上の花が咲きます。