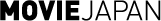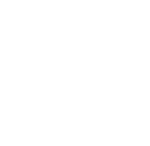- 長野 御射鹿池
- 標高1,500m、奥蓼科の山の中に静かに佇む御射鹿池は、東山魁夷の「緑響く」のモチーフにもなったことで知られています。
鏡のような水面に映るカラマツ林は、春には新緑、夏には深い緑、秋には黄金色、そして冬には真っ白な雪と氷に閉ざされ、季節ごとに大胆に色を変え、美しい風景を見せてくれます。
- 神奈川 鎌倉 長谷寺
- 鎌倉の名刹「長谷寺」の歴史は奈良時代まで遡ります。花のお寺として親しまれ、初夏には青、紫、ピンクと色鮮やかなアジサイに彩られます。境内にある見晴らしのいい眺望散策路は、この時期のみ名前も「あじさい路」になります。路には愛らしい良縁地蔵が迎えてくれます。
- 軽井沢レイクガーデン
- 軽井沢レイクガーデンは豊かな湖を取り囲むように、約400種類のバラと300種の宿根草が1年を通して四季折々に美しい表情を見せてくれます。特に6月のバラのシーズンはすべてが色とりどりのバラで彩られ、まるで童話の世界にいるようです。朝はバラの香りのゴールデンタイムと言われ、まるでバラに包まれているような気分になります。
- 東京 多摩川台公園の紫陽花
- 多摩川沿いの大田区多摩川台公園には、7種3000株の紫陽花が咲き誇ります。額あじさいは日本原産の花。花序の周辺部を縁取るように並び、園芸では、額咲きと呼ばれます。花序が球形ですべて装飾花となったおなじみのアジサイは、手まり咲きと呼ばれます。
- 山梨 河口湖のラベンダー
- 河口湖では初夏になると10万本に及ぶラベンダーが咲き誇ります。香り高い紫の絨毯は初夏の風物詩です。6月から7月にかけては河口湖ハーブフェスティバルも行われ、河口湖南岸の八木崎公園では最も多くのラベンダーを観賞することができます。北岸の大石公園では富士山と河口湖を背景にラベンダーを眺めることもできます。
- 京都 祇王寺 苔寺
- 京の嵯峨野にある小さな寺には、悲恋の物語が残ります。祇王というのは女性の名です。平清盛に寵愛を受けた祇王でしたが、清盛の心変わりと共に都を追われ、当時の往年院に出家します。明治を迎え、廃寺された往年院でしたが、後に再興され、祇王寺とされました。苔庭としても有名で沢山の種類の苔が季節ごとにその濃淡を変え、表情を変えて行きます。
- 京都 嵯峨野 竹林の道
- 嵐山の代表的な観光名所は渡月橋の北側に位置します。数万本にもおよぶ竹林の中にその散策道はあります。澄んだ空気の中で感じる竹林からの木漏れ日や、笹の重なり奏でる音はあなたを包み、癒しの世界へと案内してくれます。人の少ない静かな朝がおすすめです。
- 香川 エンジェルロード
- 恋人の聖地としても知られる香川県のエンジェルロードは1日に2回、干潮の時にのみ姿を現わす美しくも儚い場所です。そのため様々なドラマや映画で撮影地となっています。干潮の前後2時間ほどだけ小豆島と沖合の余島をつなぐ道では、大切な人と手を繋いで渡ると天使が願いを叶えてくれるという言い伝えがあります。
- 高知 仁淀川
- 5年連続で最も良好な水質として全国一位に選ばれた仁淀川。仁淀川の透明度が高く美しい青色は「仁淀ブルー」とも呼ばれ、春のひょうたん桜や秋の紅葉など、四季折々で変わるその様相は一年を通して楽しむことができます。また、中津渓谷や安居渓谷も観光名所として知られています。
- 軽井沢 白糸の滝
- 白糸の滝は自然豊かな国有林内にある景勝地。
岩から染み出した無数の滝が“白糸”のように流れ落ちる様から、その名前が付けられました。
高さ約3mの滝が、緩やかなカーブを描きながら約70mも続いていて、同じ高さから無数の滝が流れ落ちる様は、水のカーテンのようです。
- 鎌倉 明月院 あじさい寺
- 明月院は、山里にひっそりと佇む北鎌倉の禅寺で、あじさい寺として有名です。「ヒメアジサイ」という品種は澄んだ青色が特徴で、その美しい色彩は「明月院ブルー」と呼ばれています。
- 富山 黒部ダムの放水
- 黒部川最上流に建設されたダムで、186mの高さは現在も日本一です。建設工事は、7年もの歳月がかかり、そのスケールの大きさと困難さから「世紀の大事業」と呼ばれました。完成当時、大阪府の電力需要の50%を賄うほどのものでした。