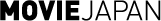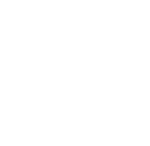- 長野 内山牧場 大コスモス園
- 標高1200mの高原に秋の風が香る頃、内山牧場のコスモス園は一面の桃色に包まれます。過去、牛の放牧地であった丘陵3haに悠々と咲くコスモスに私たちは息を呑むでしょう。またコスモス畑の背景には荒波を越えていく船のような形から名付けられた荒船山が見えます。どちらも妙義荒船佐久高原皇帝公園内にある絶景です。
- 中秋の名月
- 十五夜(中秋の名月)は四季の中でも特に月がきれいに見える日。日本では古くから月を愛でる風習がありました。お供えのススキは稲穂に似ているから収穫を祈るものとして。また魔除けとして。丸い月見団子は十五夜にちなんで十五個山のように積みます。
- 石川 お熊甲祭
- お熊甲(おくまかぶと)祭りは、末社19社が高さ20mの深紅の枠旗と神輿の行列を整え、天狗の面をつけた猿田彦を先頭に「イヤサカサー」の掛け声とともに次々と本社へ向かい、本社では式後、豊作と豊漁の喜びを表し20人の猿田彦が乱舞します。能登が培ってきた文化の多様性を示す貴重な祭りと言えます。
- 奈良 采女祭
- 采女祭は、春日大社の末社である采女神社の例祭で、毎年中秋の名月に行われます。約600年の歴史を持つ行事で、その昔、帝の寵愛を受けていた采女が、帝からの愛が薄れたことを悲観して猿沢池に入水したことから、その霊を供養する祭が行われるようになりました。祭では、秋の七草を装飾した花扇が猿沢池までを練り歩きます。
- 富山 越中八尾 おわら風の盆
- おわら風の盆は、毎年9月1日から3日にかけて行われる祭事です。越中おわら節の音に乗って、踊り手たちが町中を舞い歩きます。優雅な女踊り、勇壮な男踊りなど踊りの種類は様々です。哀愁溢れる胡弓の音色が盆の雰囲気を掻き立てます。とやまの文化財百選にも選ばれている祭りで、起源は江戸時代まで遡ると伝えられています。
- 大阪 岸和田だんじり祭
- 岸和田だんじり祭は、関西各地で行われるだんじり祭のひとつです。だんじりとは、祭礼で奉納される山車を意味する西日本特有の呼称で、重さ4tにも及ぶ絢爛豪華な見栄えをしています。血気盛んなこの祭は、「けんか祭」の異名を持ち、勢い良く突き進むだんじりを方向転換させる大迫力の「やりまわし」が見所となっています。
- 埼玉 巾着田曼珠沙華まつり
- 埼玉県日高市の巾着田では、毎年9月中旬から下旬にかけて約500万本の曼珠沙華が見頃を迎えます。直径約500m、面積は22haに及ぶ巾着田が曼珠沙華の開花により赤い絨毯を敷き詰めたように深紅に染まります。巾着田曼珠沙華まつりは例年9月中旬に行われ、花々を観賞しながら特産品販売、特別イベントなどを楽しむことができます。
- 滋賀 びわ湖テラス
- びわ湖テラスは標高1100mから湖を一望することができるリゾート施設です。打見山と蓬莱山、2つの山頂には大自然を楽しめる高級感ある展望デッキが構えています。これらの絶景スポットにはロープウェイで登ることができます。空から琵琶湖を眺めているようなテラス、その外には湖に面した白亜の空間、恋人の聖地もあります。
- 福島 会津 たかつえそば畑
- 南会津町・高杖原は寒暖差のある気候からそば作りが盛んで、日本最大級の「たかつえそば畑」の広さは12haで東京ドーム2.5個分の広さがあります。初秋には、そばの花が満開となり、観光客を楽しませています。
- 東京 府中 大國魂神社 秋季祭くり祭り
- 大國魂神社の秋季祭である「くり祭」はその名の通り「栗」の祭です。その例祭に合わせ奉納されるのが府中の郷土芸能「府中囃子」。囃子の曲にはそれぞれ踊りがあり、子供たちがオカメやヒョットコの道化、天狐や獅子に扮し競演します。
- 富山 世界遺産 五箇山
- 昔と変わらない小川の流れや田んぼのあぜ道、合掌造りの家々。素朴でこじんまりとした農村集落は、日本の原風景そのものです。また、五箇山は民謡の宝庫として知られ、「こきりこ」や「麦屋節」「といちんさ」などの民謡がうたい踊りつがれ時代を越えて息づいています。
- 鳥取砂丘
- 十万年の歳月をかけて積み上げられた偶然の造形美。
南北2.4km、東西16km、高低差最大90mの巨大な砂場は圧倒的な存在感、世界観です。