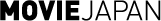祭り
- 宮城 塩竈みなと祭
- 塩竈みなと祭は、「管絃祭」「貴船まつり」と合わせて、日本三大船祭りとされているものです。毎年、海の日に開催され、神輿が市内を練り歩いた後、塩竈港から御座船に乗り入れて海上を回ります。海上では100隻を超える漁船が大漁旗をあげて追随し、太鼓や笛で盛り上げます。パレードや花火などもあり、見所満載の祭りです。
- 富山 越中八尾 おわら風の盆
- おわら風の盆は、毎年9月1日から3日にかけて行われる祭事です。越中おわら節の音に乗って、踊り手たちが町中を舞い歩きます。優雅な女踊り、勇壮な男踊りなど踊りの種類は様々です。哀愁溢れる胡弓の音色が盆の雰囲気を掻き立てます。とやまの文化財百選にも選ばれている祭りで、起源は江戸時代まで遡ると伝えられています。
- 愛媛 うわじま牛鬼まつり
- うわじま牛鬼まつりは、毎年7月にガイヤカーニバルを皮切りに行われる夏祭りです。四国有数の夏祭りとされていて、祭りが開催される3日間は何体もの牛鬼が市内を練り歩きます。また、伝統の宇和島おどりや宇和海を彩る花火なども見物です。最終日には三体の御輿が登場し、松明の火を灯しながら荘厳な走り込みが行われます。
- 鳥取しゃんしゃん祭
- 鳥取しゃんしゃん祭は毎年8月中旬に開催され、伝統的な踊りである「因幡の傘踊り」が披露されます。傘に付けられた鈴が「しゃんしゃん」と鳴ることから、この名が付けられました。祭りの目玉である一斉踊りでは、数千人の踊り手が傘を手に市内を舞い歩きます。世界最大の傘踊りとしてギネス世界記録にも認定される祭りです。
- 大阪 岸和田だんじり祭
- 岸和田だんじり祭は、関西各地で行われるだんじり祭のひとつです。だんじりとは、祭礼で奉納される山車を意味する西日本特有の呼称で、重さ4tにも及ぶ絢爛豪華な見栄えをしています。血気盛んなこの祭は、「けんか祭」の異名を持ち、勢い良く突き進むだんじりを方向転換させる大迫力の「やりまわし」が見所となっています。
- 石川 能登 石崎奉燈祭
- 石崎奉燈祭は毎年8月に開催されるキリコ祭りであり、石崎八幡神社の祭礼です。奉燈祭は七尾市の三大祭のひとつで、能登に数多くある祭りの中で最も勇壮なものとして知られています。高さ10m以上、合計6基の奉燈の正面には縁起の良い文字を、裏には勇壮な武者絵が描かれます。囃子音と灯りが浮き上がる奉燈の姿は圧巻です。
- 和歌山 那智の火祭
- 那智の火祭りは正式名称「扇祭」と呼ばれ、無形民俗文化財に指定されています。水を生命の源、火を万物の活力と見立て、五穀豊穣を祈念する祭りです。白装束を着た男性が重さ50㎏にも及ぶ燃え盛る大松明を担ぎ、那智の滝に続く石段をハリヤーの掛け声と共に練り歩きます。12体の扇神輿には熊野の神々が宿るとされています。
- 山形 まんだらの里 雪の芸術祭
- 「まんだらの里」は、東村山郡山辺町の山道を抜けた先にあります。雪の芸術祭では、ライトアップされた雪のオブジェや、花火の打ち上げ、ステージでの様々なイベントなどが楽しめます。そして、お祭のハイライトは、夜空を彩るスカイランタンの打ち上げ。冬の夜空に舞うランタンの幻想的な風景に、ただただ魅了されてしまいます。
- 青森 八戸三社大祭
- 八戸三社大祭は、ユネスコ世界無形文化遺産などに登録されている青森の伝統的な祭礼です。300年の歴史を誇り、龗神社、長者山新羅神社、神明宮の三神社からなる神輿行列や、豪華な装飾を施した高さ10m、幅8mにもおよぶ山車が見所となっています。その他にも様々な郷土芸能が披露され、日本の夏を熱く盛り上げます。
- 静岡 法多山尊永寺 万灯祭
- 法多山尊永寺は高野山真言宗の別格本山です。法多山では7月10日が1年で最もご利益のある日とされています。また、この日に本尊厄除観世音に灯りを献することでご利益は倍増するとも言われています。万灯祭は本堂前に何千基もの灯籠が奉納される夏の風物詩です。境内に灯る幻想的な灯籠の他にも、寄席などの催しで賑わいます。
- 東京 上野 入谷朝顔まつり
- 入谷朝顔まつりは、七夕の季節に東京台東区の入谷鬼子母神周辺で行われる祭事です。早朝5時から23時までと、一日中楽しめるこの祭りは、江戸時代後期からはじまりました。道々に並べられる色鮮やかな朝顔の数は12万鉢にも及び、屋台や露店も朝顔に負けじと賑やかに祭りを盛り上げます。夏の風物詩を味わう伝統の祭りです。
- 東京 浅草寺ほおずき市
- 浅草寺のほおずき市は、1日で46000日分の功徳を得られるとされる縁日に合わせて行われるものです。46000日というのは、126年、つまり人間の一生分以上の功徳が得られる日であると言えます。ほおずきは健康祈願や、盆の棚飾りに用いられます。境内には朝から晩まで、ほおずき売りたちの賑やかな声が響き渡ります。